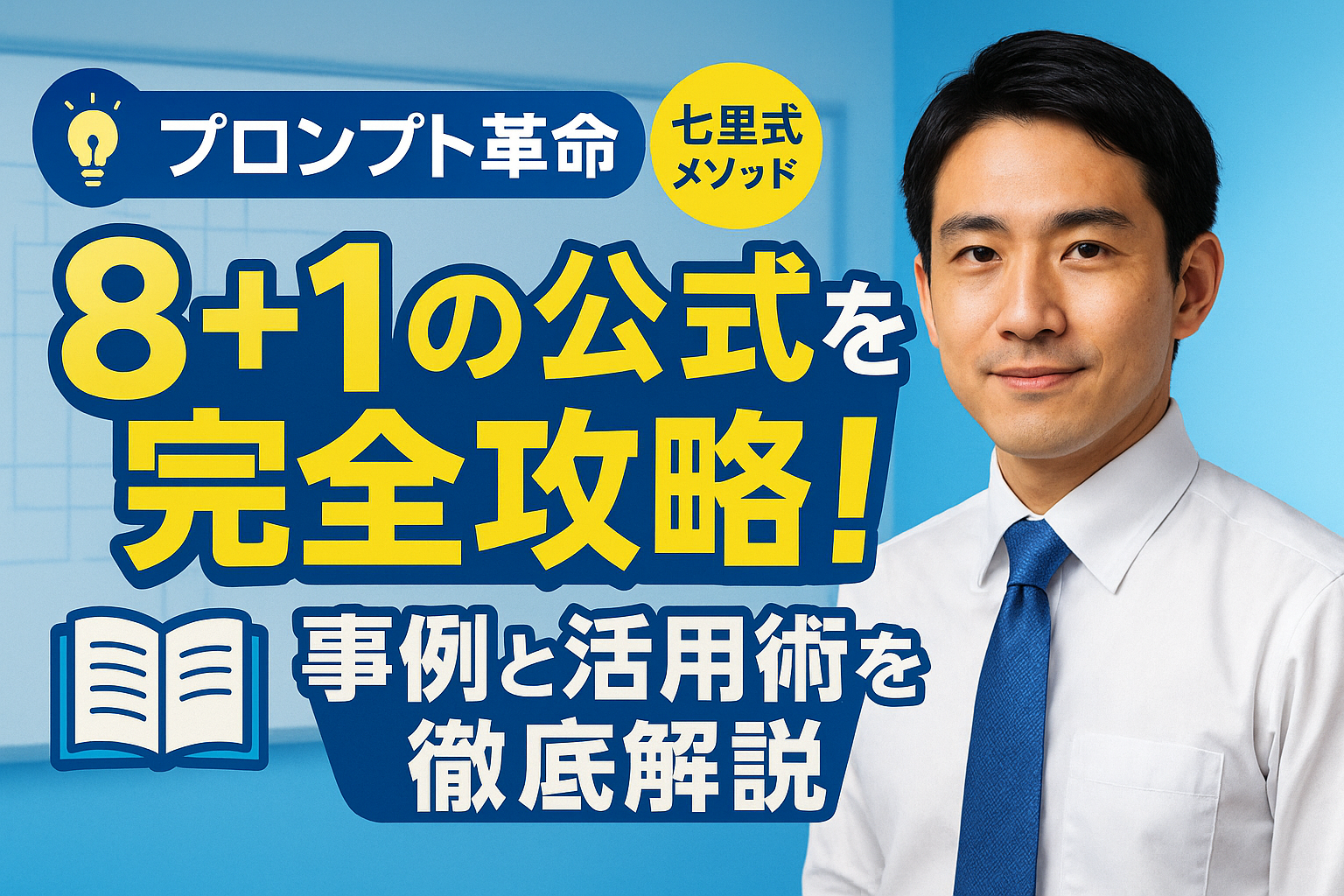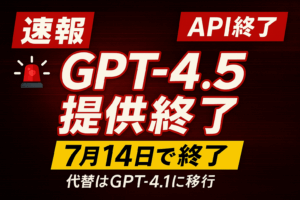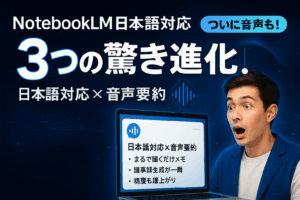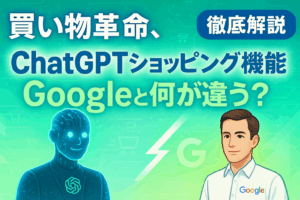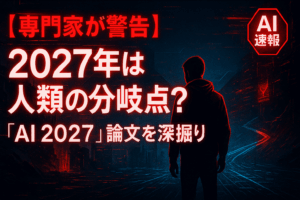「ChatGPTを使ってみたけれど、なんだか思ったような答えが返ってこない…」
「もっとAIをうまく活用して、仕事やブログに役立てたい!」
そんなふうに感じていませんか?
実は、AIの力を最大限に引き出すカギは、私たちがAIに伝える「指示=プロンプト」にあるのです。
なかでも今、大きな注目を集めているのが、日本のAIエンジニア・七里信一氏が考案した 「七里式プロンプト(8+1の公式)」。
まるでAIに“人間のように”考えさせ、こちらの意図を的確に読み取らせる——まさに魔法のようなプロンプトの公式です。
この記事では、その「8+1の公式」の全貌を、初心者の方にもわかりやすく徹底解説。
さらに「クライアントへのアポ取りメール作成」や「読者を惹きつけるブログ記事のアイデア出し」といった、すぐに使える実践事例もご紹介します。
この記事を読み終えるころには、あなたも七里式プロンプトを使いこなし、ChatGPTのポテンシャルを120%引き出せるはず。
七里式プロンプト「8+1の公式」とは?AIとの対話を変える鍵
ChatGPTをはじめとする生成AIは、私たちの働き方や情報収集の方法に、かつてない革命をもたらしています。
しかし、その可能性を最大限に引き出すためには——ただ質問を投げかけるだけでは不十分です。
重要なのは、「どう尋ねるか」。
つまり、プロンプト(指示文)の質が、AIから得られる回答の質を決定づけるのです。
漠然とした問いかけでは、AIも戸惑います。
その結果、どこかで見たような、表面的な回答しか返ってこない……そんな経験、ありませんか?
そこで登場するのが、日本のAIエンジニア・七里信一氏が考案した、「七里式プロンプト」。
これは、AIとのコミュニケーションをもっと的確に、もっと効率的に行うための、構造化された指示のフレームワークです。
その中核をなすのが、本記事で詳しく解説する 「8+1の公式」。
では、この公式が目指すものとは何か?
それは、AIを単なる計算機や検索エンジンとして使うのではなく、
“人間のように”文脈を理解し、考え、あなたの意図を深く汲み取らせること。
人と人の会話には、「空気」や「前提」「流れ」といった暗黙の了解があります。
でもAIには、それがありません。
だからこそ、私たちが“伝え方”をアップデートする必要があるのです。
七里式プロンプトの「8+1の公式」は、そのための最適な設計図。
具体的には、以下の9つの要素から構成されます:
- 前提条件
- 対象プロファイル
- 参考情報
- 実行指示
- 形容詞
- 出力形式(文章)
- 出力形式(形)
- スタイル
- 追加指示
これらを順序立てて伝えることで、まるで優秀な右腕と会話しているかのような、的確で再現性の高いアウトプットが得られるようになります。
もちろん、世の中には他にも魅力的なプロンプト設計法があります。
たとえば、深津式プロンプト、シュンスケ式ゴールシークプロンプト、7Rプロンプトなど。
それぞれ個性的な手法ですが、七里式の「8+1の公式」は、特にその網羅性と構造の明快さが光ります。
初心者でも理解しやすく、すぐ実践に移せる。
だからこそ、AI活用の“型”を身につけたい方には、うってつけなのです。
次の章では、この「8+1の公式」を構成する9つの要素を、ひとつずつ丁寧に解説していきます。
【図解あり】「8+1の公式」9つの構成要素を徹底解説!
七里式プロンプト「8+1の公式」の全体像を掴んでいただいたところで、
ここからはその心臓部である9つの構成要素について、一つひとつ詳しく解説していきます。
それぞれの要素がどんな役割を果たし、AIの思考をどう導くのか。
これを理解することが、効果的なプロンプト作成への第一歩となります。
要素①:前提条件 ─ タスクの全体像を示す羅針盤
最初に設定すべきは「前提条件」。
これはAIに、何を、誰のために、どうして欲しいのかを明確に伝えるためのベースです。
具体的には以下を含みます:
- タイトル(何の指示か)
- 依頼者条件(誰が求めているのか)
- 制作者条件(AIにどんな役割を期待するのか)
- 目的と目標(何を達成したいのか)
人間同士でも「これは誰からの依頼で、ゴールは何か」が分からなければ動けませんよね。
AIにも同じように、**方向性を示す「地図」**を渡してあげる必要があります。
要素②:対象プロファイル ─ 誰に届けるのかを明確にする
次は、アウトプットの受け手を定義します。
年齢、性別、職業、興味、悩みなどの詳細なプロファイル設定がポイント。
たとえば「健康レシピ」を依頼する場合、
「子育て中の主婦」と「ジム通いの会社員」では、響く内容が全く違います。
この要素を盛り込むことで、AIはパーソナライズされた回答を生成しやすくなります。
要素③:参考情報 ─ 思考の材料を提供する
AIは万能のように見えて、リアルタイムの情報や文脈、あなた固有のデータにはアクセスできません。
そこで、補足すべき情報や、前提知識、参考URL、キーワード、既存文章などを提供します。
これは、AIに**燃料(インプット)**を与える作業です。
材料が揃えば、AIのアウトプットも格段に深く、具体的になります。
要素④:実行指示 ─ 名詞と動詞で「何をすべきか」を指示
ここがAIへの具体的な行動命令部分です。
ただ「〜してください」と曖昧に言うのではなく、
「{対象}に対して、{参考情報}を使い、{行動(名詞+動詞)}」という構文で伝えるのがコツ。
例:
×「ブログを書いて」
〇「30代経営者向けに、コンサルティングの魅力を伝えるブログ記事を作成してください」
AIに**“行動の型”を与える**ことで、迷いなく出力してくれます。
要素⑤:形容詞で精度を上げる ─ 回答の質をデザインする
AIにどんな雰囲気・トーン・精度を求めるかを伝えるのがこのステップ。
「わかりやすい」「説得力のある」「簡潔な」「ユーモラスな」など、形容詞で方向性を指定しましょう。
これだけで、同じ内容でもアウトプットの印象がガラリと変わります。
要素⑥:出力形式(文章) ─ 読みやすさを整える
文章の形をどうしたいかを伝える要素です。
たとえば:
- 箇条書きで
- 段落形式で
- メール形式で
- レポート風に
これを指定するだけで、そのまま使える完成度の高い出力が得られます。
要素⑦:出力形式(形) ─ 情報の見せ方を設計する
文章構成だけでなく、見た目のレイアウトや構造にも指示を出せます。
「マークダウン形式で」「表にまとめて」「見出しをレベル分けして」など。
この要素は、視認性と情報整理力に大きく関わります。
要素⑧:スタイル ─ AIに“人柄”を持たせる
文体や口調を指定することで、アウトプットに個性や温度感を加えます。
「プロフェッショナルに」「カジュアルに」「親しみやすく」「共感を込めて」など、
ターゲットに合わせて最適な“人格”を設定しましょう。
要素⑨:追加指示(+1) ─ 最後の仕上げで完成度を高める
最後のこの「+1」が、プロンプトの微調整&最適化パートです。
- 文字数制限を加える
- 特定のキーワードを含める
- 引用元やURLを明記させる
- 説明を初心者向けにする
など、AIの出力に対する最終的なディレクションを行います。
これら9つの要素を意識してプロンプトを構成することで、
AIとの対話は、単なる“質問と回答”から一歩進んだ、共創型のコミュニケーションへと進化します。
次は実際に、この「8+1の公式」を使ったプロンプト作成の実例を見てみましょう——
【事例で学ぶ】「8+1の公式」を使ったプロンプト作成例
理論を学んだら、次は実践です。
ここでは、「8+1の公式」が実際にどのように活用できるのかを、ビジネスやブログ運営の現場で役立つリアルなケーススタディを通じてご紹介します。
それぞれの要素が、どのようにプロンプトに落とし込まれ、どのような出力につながるのか。
そのプロセスを体感しながら、**プロンプト作成の“型”**を習得していきましょう!
ケーススタディ1:新規クライアントへのアポイント依頼メール作成
1. シチュエーション設定
あなたは、中小企業向けSaaS「Efficiency Pro」を提供する企業の営業担当者・佐藤さん。
資料請求をしてくれた株式会社ABCの田中様に対し、オンライン商談のアポイントを依頼するメールを作成したいと考えています。
「失礼なく丁寧に、でもしっかり商談につなげたい」——
そんな場面に、AIと“いい関係”を築くプロンプトが力を発揮します。
2. 「8+1の公式」による要素の落とし込み
- 前提条件
タイトル:新規クライアントへのアポイント依頼メール作成
依頼者:営業担当者・佐藤
制作者:丁寧で効果的なビジネスメールを作れるAIアシスタント
目的:田中様からオンライン商談の了承を得る
目標:3日以内に返信→1週間以内に商談設定 - 対象プロファイル
相手:株式会社ABC 担当者 田中様(役職不明)
企業規模:中小企業
ニーズ:業務効率化に関心あり - 参考情報
自社サービス:中小企業向け業務効率化SaaS「Efficiency Pro」
きっかけ:田中様の資料請求
提示価値:コスト削減/生産性向上の可能性 - 名詞と動詞による実行指示
→ 上記内容を踏まえて、田中様へのアポイント依頼メールを作成してください。 - 形容詞指定
→ 丁寧な、簡潔な、相手のメリットが伝わる、信頼感のある - 出力形式(文章)
→ ビジネスメール形式 - 出力形式(形)
→ 件名・宛名・挨拶・本文(3〜4パラグラフ)・結び・署名 - スタイル
→ 礼儀正しく、誠実で信頼感のある口調 - 追加指示
→ 件名に【株式会社(自社名)】を含める
→ 商談候補日時を3つ提示
→ 文頭に資料請求のお礼を入れる
3. なぜこのプロンプトが「使える」のか?
このプロンプトでは、Who/What/Why/Howがすべて明示されているため、
AIが迷うことなく、状況に応じた的確かつ配慮あるメール文を生成できます。
特に「対象プロファイル」「参考情報」が充実していることで、
テンプレのような機械的文章ではなく、**“相手の背景に合った文脈ある提案”**を実現できるのです。
ケーススタディ2:読者の関心を引くブログ記事アイデア出し
1. シチュエーション設定
あなたは、最新ガジェット情報を発信するブロガー。
新作スマートフォン「TechPhone X」について記事を書こうと考えていますが、
同じようなレビュー記事があふれる中で、一味違う切り口を見つける必要があります。
2. 「8+1の公式」による要素の落とし込み
- 前提条件
タイトル:TechPhone Xに関するブログ記事アイデア出し
依頼者:ガジェット系ブロガー
制作者:読者心理とSEOを理解するコンテンツ企画AI
目的:読者の関心を引く記事アイデアを複数得る
目標:ユニークな記事タイトル×5本+構成案 - 対象プロファイル
読者層:20〜40代のガジェット好きな男女
知識レベル:中級者(専門用語に抵抗なし)
求めている情報:スペック+使用感+比較+活用法 - 参考情報
テーマ:TechPhone X
特徴:高性能カメラ/長時間バッテリー/AI機能
想定キーワード:「TechPhone X レビュー」「比較」「使い方」など
競合傾向:スペック解説に偏りがち - 名詞と動詞による実行指示
→ 上記を踏まえ、「読者の関心を引く独自アイデア」を5つ出してください。 - 形容詞指定
→ 独自性のある/具体的な/検索意図に合致した - 出力形式(文章)
→ 各アイデアに、タイトル+簡単な構成案(3点)をセットで記述 - 出力形式(形)
→ 番号付きリスト形式 - スタイル
→ 創造的で「知りたい!」を引き出す提案型口調 - 追加指示
→ スペック以外の切り口を重視
→ 生活シーンにフォーカス
→ ニッチな検索キーワードも含めること(例:「TechPhone X 写真 印刷」など)
3. 企画アイデアを“惹き出す”プロンプトの力
このプロンプトでは、AIに「競合との差別化が必要」「読者の生活に直結する価値が重要」というメッセージが明確に伝わっています。
そのためAIは、単なるカタログ的紹介ではなく、読者が「読みたくなる」「共有したくなる」ような、切り口の尖ったアイデアを出力しやすくなります。
▼まとめ:事例でわかった「8+1の公式」の力
- 情報の「粒度」と「順序」を揃えることで、AIの出力が見違えるほど具体的に
- 特に「対象プロファイル」「形容詞」「スタイル」は、人間らしい温度感を加える鍵
- 創造性が求められるシーンでも、「8+1の構造」がブレない軸となってくれる
次回は、あなたの実際のプロンプトをその場で添削・改善するワークショップをご紹介します。
「AIとの会話が変わる」その瞬間を、あなた自身の手で体感してみませんか?
七里式プロンプトを使いこなすメリットと注意点
― AIが“頼れる相棒”に変わる、その理由とコツ ―
ここまでで、七里信一氏が考案した「8+1の公式」——
通称七里式プロンプトの構造と、実践的な活用法を学んできました。
でも、ちょっと待ってください。
「いいのは分かった。でも、本当に効果あるの?」
「理論通りに使っても、うまくいかなかったら?」
「AIって便利そうだけど、なんか思った通りに動かないんだよな…」
そんな不安、少しでもありませんか?
実は私も、最初はそうでした。
でも、「8+1の公式」という“指示の型”を身につけてから、
AIとのやりとりが、驚くほどスムーズになったのです。
ここでは、七里式プロンプトを使うメリットと、うまく使いこなすための注意点をわかりやすく解説します。
これを知っているかどうかで、AI活用の成果が2倍、3倍と変わってくるかもしれません。
なぜ七里式プロンプトは効果的なのか?
“曖昧なAI”を、“優秀な右腕”に変える8つの理由
- 明確性
→ 「何を・どうして欲しいか」を9要素に分解して伝えることで、曖昧さゼロ。
AIは迷わず、意図を“読み取る”ようになります。 - 柔軟性
→ フォーマットは共通でも、内容は自由自在。
1分で書ける簡易プロンプトも、5ステップかかる戦略設計もOK。 - 効率性
→ 修正の手間が激減。やり直し不要。
AIとの往復が少ない=時間が増える。 - 一貫性
→ 書く人が変わっても、質は安定。
チーム全体で共通言語として使える。 - 学習容易性
→ 初心者でも理解しやすく、再現性も高い。
プロンプト作成が**「苦手じゃなくなる」**。 - 精度向上
→ 「形容詞」や「追加指示」で、質感やトーンまでコントロール可能。
思い通りの表現が引き出せる。 - 文脈理解の促進
→ 前提やターゲットを伝えることで、AIが“なぜそれを求めているのか”を把握。
ズレた回答が激減します。 - 創造性の向上
→ 「型」によって基盤が整うと、人間はもっと自由になれる。
あなたの“ひらめき”を邪魔しない、むしろ引き出す土台になるのです。
失敗しないための注意点とベストプラクティス
― AIの“誤解”を防ぐ7つのチェックポイント ―
- 簡潔に書くこと
→ 情報過多は逆効果。詰め込みすぎず、芯を伝える。 - 具体的に指示する
→ 「いい感じ」では伝わらない。“何がどう良いのか”を言語化する。 - 倫理的に配慮する
→ AIが暴走しないように。差別・誹謗・著作権への配慮は必須。 - 定期的に見直す
→ モデルの進化に合わせてプロンプトもアップデートを。
“一度作って終わり”ではもったいない。 - 出力は必ず検証する
→ AIはあくまで“優秀な補佐”。最終確認はあなたの目で。 - 全要素を入れなくてもOK
→ 重要なのは“バランス”。内容に応じて、要所だけ使えばいい。 - スタイルと内容の整合性
→ 砕けた文体で専門論文を書く…そんなミスマッチは避けましょう。
【経験談】私が七里式プロンプトで感じた変化
私自身、この七里式プロンプトを使い始めてから、ChatGPTとの向き合い方が大きく変わりました。以前は、まるで気まぐれな部下に指示を出すような感覚で、なかなか意図通りに動いてくれず、試行錯誤の連続でした。
しかし、「8+1の公式」という”型”を知ってからは、AIに何をどう伝えれば良いかが明確になり、驚くほどスムーズに、そして的確に、私の求めるアウトプットを出してくれるようになったのです。
特に、ブログ記事の構成案を作る際、以前は1時間以上かかっていた作業が、今では15分程度で質の高い叩き台が完成します。
これにより、空いた時間でリサーチを深めたり、表現を練り上げたりすることに注力できるようになり、記事全体のクオリティ向上にも繋がっています。)
これらのメリットを最大限に活かし、注意点を守ることで、七里式プロンプトはあなたのAI活用を力強くサポートしてくれるはずです。
まとめ
この記事では、ChatGPTをはじめとする生成AIの可能性を、最大限に引き出す鍵——「七里式プロンプト『8+1の公式』」について解説してきました。
構造の全体像から、9つの要素の役割、具体的なビジネス応用事例、そして、使いこなすためのメリットと注意点まで。
あなたの中にも、少しずつ「AIとの向き合い方」が変わってきた感覚があるのではないでしょうか?
もう、曖昧な指示でモヤモヤする必要はありません。
「8+1の公式」というフレームを使えば、
AIに“的確な思考の地図”を手渡すことができるのです。
前提条件・対象プロファイル・参考情報・実行指示・形容詞
出力形式(文章/形)・スタイル・追加指示
この9つの要素を組み合わせるだけで、
あなたの言葉は、AIにとってクリアで実行可能な指示へと変わります。
実際にご紹介した「アポイント依頼メール」「ブログ記事アイデア出し」のように、
この公式は、営業、企画、ライティング、リサーチなど、あらゆるビジネスシーンで活用可能です。
さあ、今日からあなたも「8+1の公式」を試してみませんか?まずは簡単なタスクからで構いません。この記事を参考に、自分なりのプロンプトを作成し、AIとの対話の変化を実感してみてください。